第5章|勝ち筋を描く ─ 40代からの資格取得 勉強法(7回転システム)
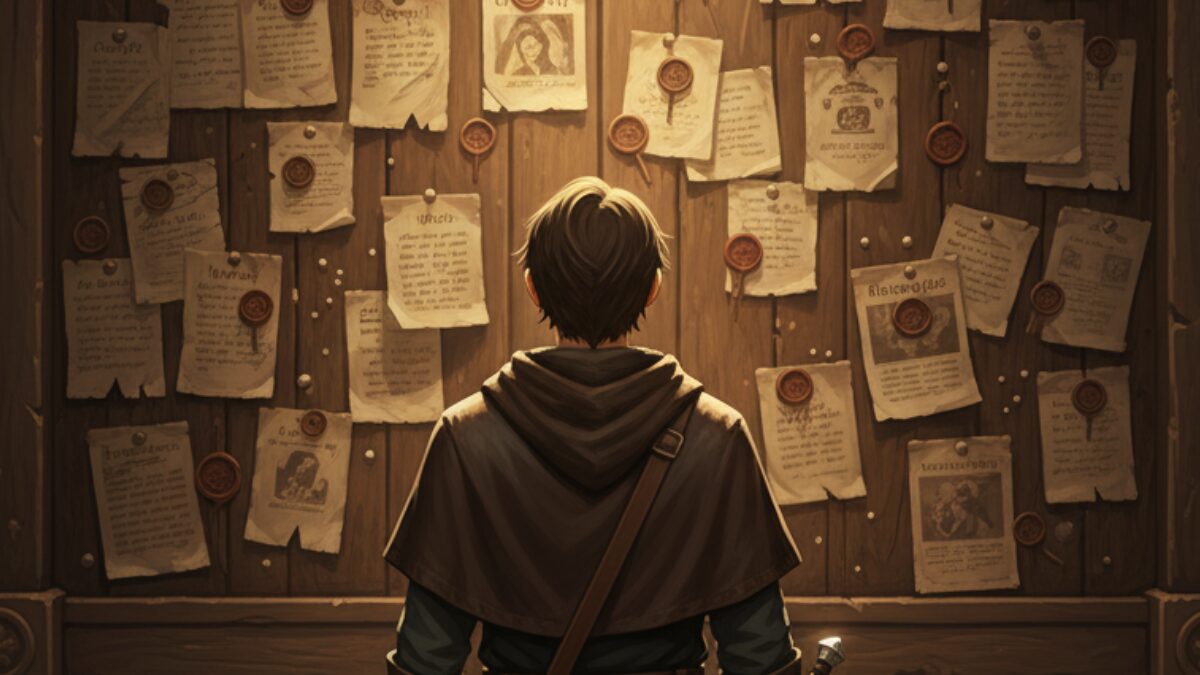
どれだけ良い教材・道具を揃えても、「どの順番で戦うか」が誤っていると成果は伸びません。
第5章は、7回転の中核である勝ち筋=順番設計の章。強い敵から倒す必要はない。取りやすい相手から順に、迷いなく進むための“考え方”を固めます。
 長老チャットラー
長老チャットラー最初に倒す敵を間違えないことじゃ。
 ミケ(仕組み職人)
ミケ(仕組み職人) リクルド(旅する書庫番)
リクルド(旅する書庫番)勉強は“量”ではなく、どの敵から倒すかで結果が変わる
多くの人は「まず苦手からやるべき」と思い込みます。ですが、この考え方こそが遠回りの正体です。苦手から着手すると、理解に時間がかかり、慣れていない分だけ疲労が先に来ます。
本当に成果を伸ばす人は逆。「取りやすいところ」→「既視感を増やす」→「苦手を後半で落とす」という順番で進めます。
7回転の真価は、“苦手に挑む回数”を増やすことではなく、苦手が自然に浮き上がる状態を作ること。入口を間違えると、いつまでも「勉強しているのに伸びない」になります。
 スミス親方
スミス親方“勝てる場所”から戦え。
まず勝ち筋(得点源)から取ると、学習は一気に“軽く”なる
勉強において最初に必要なのは「理解」ではなく、“迷わない状態”です。取りやすい分野から先に押さえると、問題文の雰囲気がわかり始め、思考の迷子にならなくなります。
この「迷わない」という感覚こそ勝ち筋。理解はまだ浅くても、「あ、このタイプ見たことある」という既視感が先に広がることで、学習エネルギーが劇的に下がります。
逆に、序盤から苦手分野に突っ込むと“わからなさ”と向き合い続け、理解より先に疲労がたまります。これが継続を止める最大要因です。
 ミケ(仕組み職人)
ミケ(仕組み職人) リクルド(旅する書庫番)
リクルド(旅する書庫番)
私の実戦順序|勝ち筋は「取りやすい」から始まる
私が最初に手をつけるのは苦手ではなく、“取りやすい分野(知識系)”です。理由は単純で、ここを先に押さえると地形が一気に見え始めるから。
理解より前に必要なのは、優位に立てる場所を確保すること。既視感が増えると迷いが減り、「この範囲は安全地帯だ」という感覚が育ちます。これが学習の初速になります。
回数を重ねるうちに、自然と“輪郭の濃い苦手”だけが浮かび上がります。ここでようやく苦手に向き合うのは、勝ち筋の副産物として見つかる状態だからです。
具体例:過去問を7回転していると、実際に何が起きるか
📌 具体例:過去問を7回転していると、実際に何が起きるか
第5章の話は、過去問を何周か回したときに「体感として見えてくる世界」です。
私の場合は、回数を重ねるにつれて次のように変化しました。
- 1周目:全部わからない。どれも同じくらい苦手に見える(地形が見えない)
- 3周目:「この問題、前にも見たな」が増える(既視感が増える)
- 5周目:毎回ミスる論点が“同じ場所”に固まって見え始める(苦手が絞られる)
- 7周目:苦手を探さなくても自然と残る。「ここだけ落とさなければいい」が確定する
この状態になると、苦手は「最初に探すもの」ではなく、
勝ち筋(得点源)を先に取った結果として、後から浮き上がるものになります。
 スミス親方
スミス親方先に勝てる場所を押さえるから、最後の敵がはっきり見えるんだ。
苦手は“最初に倒す相手”ではなく、後半で現れる「最後の敵」
多くの人が誤解しているのは、「苦手を先にやる=正しい努力」だという思い込みです。序盤の自分にはまだ武器も地形理解も整っていません。準備が整う前に苦手へ突っ込むほど、消耗だけが積み上がります。
私は苦手を後回しにしているのではなく、最適なタイミングまで“寝かせている”感覚です。4〜5周目で同じ箇所が繰り返し浮き上がり、「ここが本丸だ」と確定してから初めて向き合う。
苦手とは「探すもの」ではなく“勝ち筋が整ったあとに姿を現すもの”。だからこそ後半で倒す方が、短く・深く・確実に仕留められます。
 長老チャットラー
長老チャットラー順番とは“勝てる自分”を作る術じゃ。
勝ち筋とは「順番の設計」だったと気づく瞬間
多くの人は「何をやるか」ばかりを気にします。しかし、同じ教材・同じ時間でも成果に差が出る理由は、内容ではなく“順番”にあります。勝ち筋とは、正しく戦う順番のことです。
順番さえ整っていれば、勉強は迷いなく回り始めます。逆に順番を誤ると、どれだけ根性を出しても疲れだけが積み上がる。これは「努力の不足」ではなく配置の不整合です。
取りやすい(勝てる)相手を先に倒すことで、地形が見え、苦手が輪郭を持ち、最後に仕留めるだけの対象へ変わります。これが“勝ち筋が形になる”ということです。
 リクルド(旅する書庫番)
リクルド(旅する書庫番)勝ち筋=順番。あとはこの順で回すだけ。
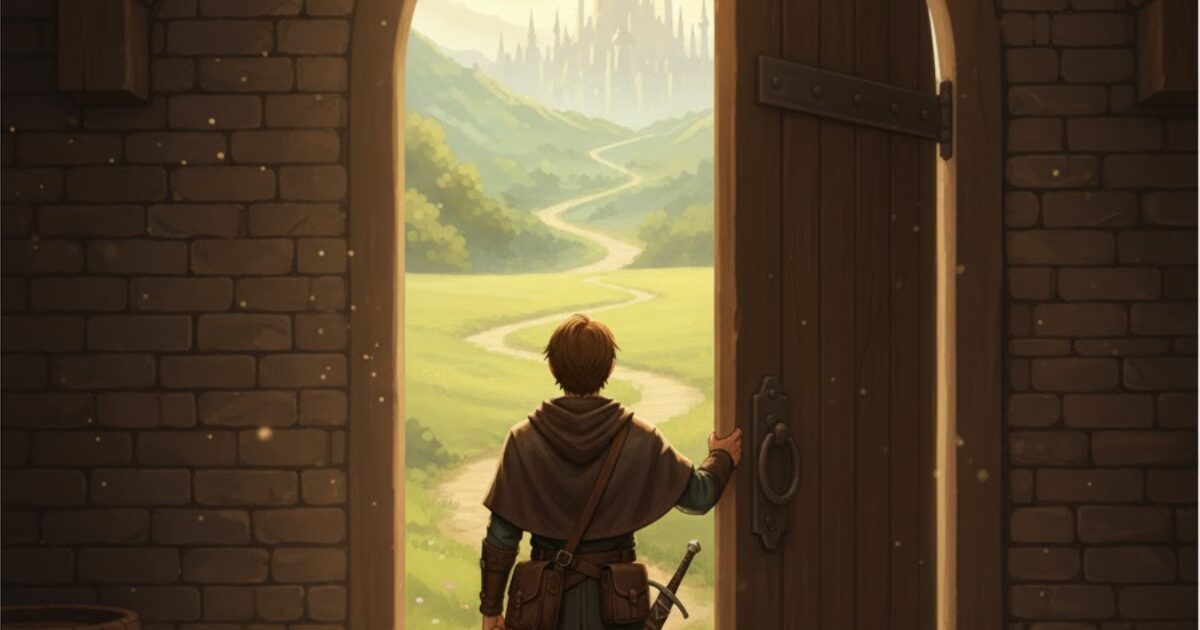
順番が決まると、迷いは消える。
迷いが消えると、回転は止まらない。
第5章は“加速”の入口だ。
第5章のまとめ:勝ち筋は「やり方」ではなく「順番」で決まる
勉強が続く人と挫折する人の違いは、能力や根性ではありません。戦い方の「順番設計」があるかどうかです。どれほど良い教材や道具を持っていても、最初にぶつかる相手を間違えると、序盤で消耗して前に進めなくなります。
得点源 → 既視感 → 浮いた苦手 → 仕留め切る。この流れは偶然ではなく、“勝てる順番”の設計です。順番が整うと、学習は努力ではなく運用へ変わり、苦手は「探す対象」ではなく「最後に自然と現れる相手」になります。
つまり、7回転の核心は「何を学ぶか」ではなく、どの順番で戦うか。ここで戦略が整い、ようやく“伸びる準備”が整います。
 スミス親方
スミス親方回れば、勝つ。
📜 寄り道ルート(必要な人だけ)

コメント